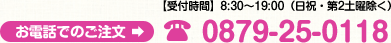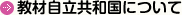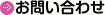すもうの置物をとおして お相撲を知ろう 陶芸和雑貨
お相撲のこと
子供たちは お相撲のこと どれくらい知っているのでしょう?
日本の国技で 伝統文化であること。
歴史は深く さかのぼると、神話の時代にたどり着きます。
日本文化に深く根ざした相撲の 珍しい 力士の置物をごらんください。
![kyouzai-j_m200-313_2[1].jpg](https://matsushita-bungu.co.jp/kyouzai/blog/udata/cache/2017/03/kyouzai-j_m200-313_2[1]-thumb-400x400-19690.jpg)
相撲はその年の農作物の収穫を占う祭りの儀式として、
毎年行われてきました。
そして これは後に宮廷の行事となって300年続きます。
鎌倉時代から戦国時代にかけての武士の時代には、武士の戦闘の訓練として
盛んに相撲が行われました。
江戸時代からは 浪人や力自慢の者の中から、相撲を職業とする人たちが現れます。
全国で相撲が行われるようになり、江戸時代の中期には相撲が興行されるようになります。
相撲は歌舞伎と並び 一般庶民の娯楽として 生活の中に大きな要素をなすようになりました。
相撲には歴史・文化・神事・競技など様々な側面があります。
行司をはじめ 江戸時代より続いている土俵入り、化粧廻しなど文化的に大変重要なものです。
![kyouzai-j_m200-336_3[1].jpg](https://matsushita-bungu.co.jp/kyouzai/blog/udata/cache/2017/03/kyouzai-j_m200-336_3[1]-thumb-400x400-19681.jpg)
本当は 土俵台と 力士と 行司さんば 別々なんですが こうやって ならべると
今にも 大勝負が始まりそうです。
![kyouzai-j_m200-325[1].jpg](https://matsushita-bungu.co.jp/kyouzai/blog/udata/cache/2017/03/kyouzai-j_m200-325[1]-thumb-400x400-19684.jpg)

立行司
勝負を裁く 木村庄之助について。
木村庄之助というのは 歌舞伎のように 代々引き継がれている名前です。
行司も力士同様に階級社会で、見習いから始まり、序二段、三段目、幕下、十枚目、三役、さらに最高位の立行司へとあがっていきます。
いわば行司の横綱が「木村庄之助」ということです。
短刀を腰に差しているのですが、差し違えたら切腹する覚悟で臨むという意味が込められているそうです
また、仕事の幅広さや覚えることの多さに驚きます。
相撲部屋の掃除や親方のお茶くみなど下働きをする以外にも、力士が場所の成績に合わせてもらう給金(褒賞金)の計算をします。
番付表や取組表に使われる〈相撲字〉という独特の文字を覚え 番付表を書きます。
本場所中は取組の決まり手を伝える場内放送と、審判部が行う取組作りに必要な過去の対戦成績などのデータ提供も担当します。
場所後に各地を回る巡業では、日程調整から交通手段、宿泊先の手配などを取り仕切ります。
力士が少しでも 気持ちよく相撲に取り組めるように サポートをしています。
いかがでしたか?
お相撲のこと ほんの少しでしたが ご紹介しました。
お相撲を見るときや、また身近にお相撲の話や
このような置物を飾るときなどに お話を添えて ぜひ子供さんに聞かせてあげてくださいね。
- 最新教材記事&動画
-
- 冷蔵庫に貼ってあるプリント類がスキっと解決!スキットマン 冷蔵庫ピタッとファイル(見開きポケットタイプ)
- 行楽シーズンの暇つぶしに最適!お子さんを飽きさせない。わくわくゲームセット
- 子供も大人も嬉しいすべらない定規。nanopita定規セット
- こんなにリアルなショベルカー。最近のダンボール工作のクオリティはすごい。
- 環境にやさしい消しゴム「PVCフリーホルダー字消し」に鮮やかな桜色が登場
- 新生活に頼れるお供。DIYに大活躍!どうぶつの工具 ラチェットドライバーセット ベアパパ
- トロフィーに寄せ書き!これは貰うと嬉しい!!メッセージトロフィー
- 様々なものを挟めて便利に使えるコンパス。マルチコンパス ブラック(梅本デザイン)
- 地味だけど役に立つすごいやつ。「ペンデメクルン」は種類も様々
- 全国のサッカー少年・少女の卵たちへ。室内でも安心して蹴れるフェルトでできたサッカーボールです。
- 卒業しても忘れない・・。最後の席順を寄せ書きに保存。学校色紙 教室
- バレンタインのメッセージカードにもピッタリ!ハラペコ喫茶 ダイカットミニレターセット チョコフロート
- 試験対策は万全に。マークシート用の鉛筆画あるのをご存知でしょうか?
- お正月に最適!遊びながら勉強もできる。日本地図おつかい旅行すごろく
- 来年は辰年!ダンボールで作れるかわいい干支の置物。ハコモ キッズ 動物シリーズ ドラゴン
- これであなたも忘年会や新年会の人気者!トランプマン監修、科学マジック入門3 コップの手品
- リバーシと絵合わせが楽しめる!クリスマスにみんなで遊びましう。
- 日々の暮らしに使える便利な折り紙。暮らしの中の折り紙(小物入れ・リングスタンド・メガネスタンド・金魚飾り)
- プロも愛用するコピックチャオ。「はじめてさんへのコピックデビューセット」であなたも使い始めてみませんか?
- もうすぐクリスマス。オシャレでかわいいクリスマスデザインのミニチュアを飾ってみませんか?
- 教材別作り方特集&動画
-
- 3Dで学ぶ【19】
- おもしろ教材【449】
- からくり箱について【22】
- さんすうについて【4】
- アニメーションについて【5】
- ブロックについて【23】
- マジック教材について【63】
- ミニチュアハウスについて【32】
- メイドインジャパンについて【18】
- ランドセルについて【14】
- ロボットについて【42】
- 音楽について【4】
- 家族&大人の工作について【140】
- 家庭科について【13】
- 科学工作について【75】
- 科学実験について【150】
- 学校教材について【14】
- 学童用品【125】
- 限定品【32】
- 工作について【372】
- 香川県限定 うどん県シリーズ【6】
- 自立学習について【12】
- 書道について【15】
- 書道筆について【9】
- 人体模型について【3】
- 地球儀について【5】
- 動物模型について【9】
- 美術教材について【32】
- 防災【6】
- 万年筆について【10】
- 遊び&創意教材について【264】
- 幼児玩具について【86】
- 幼児教材について【92】
- 理科について【103】
- 理科実験について【174】